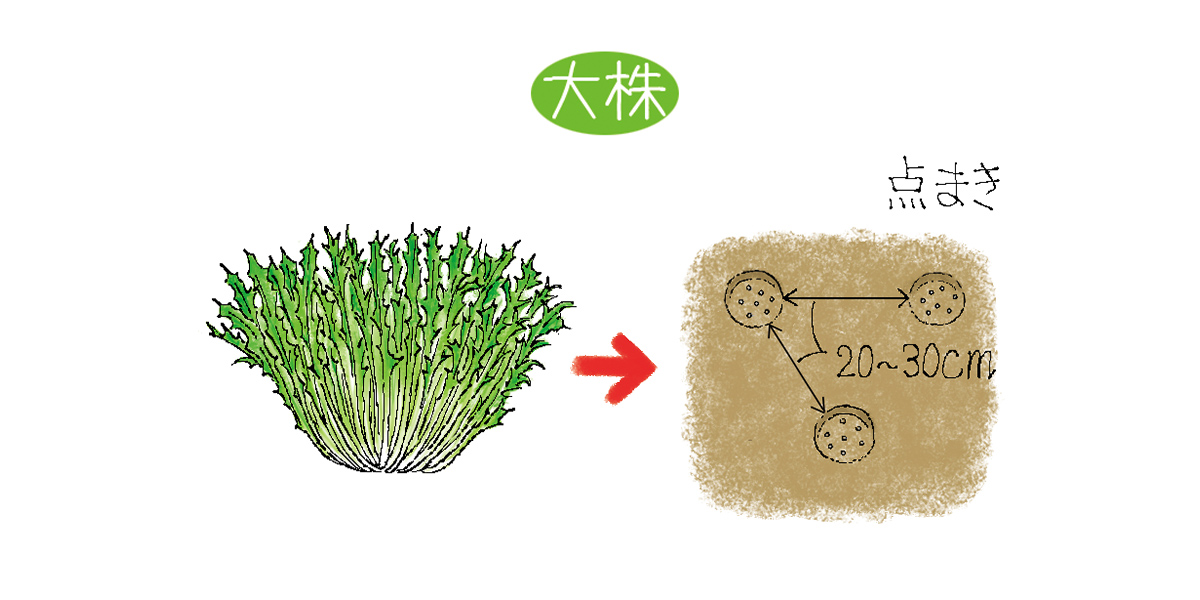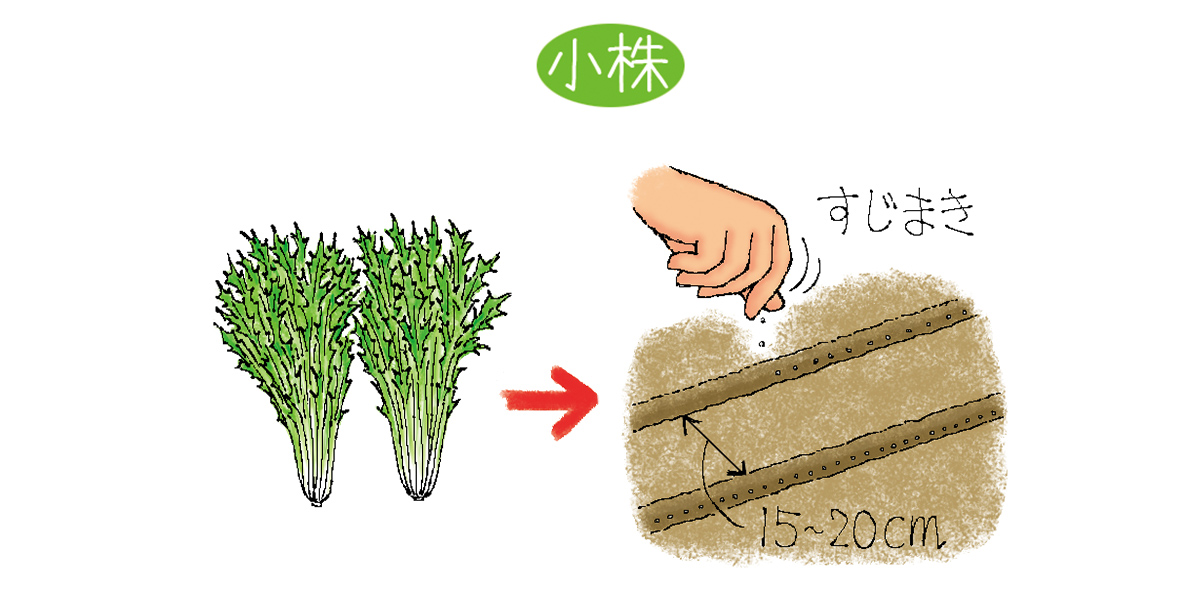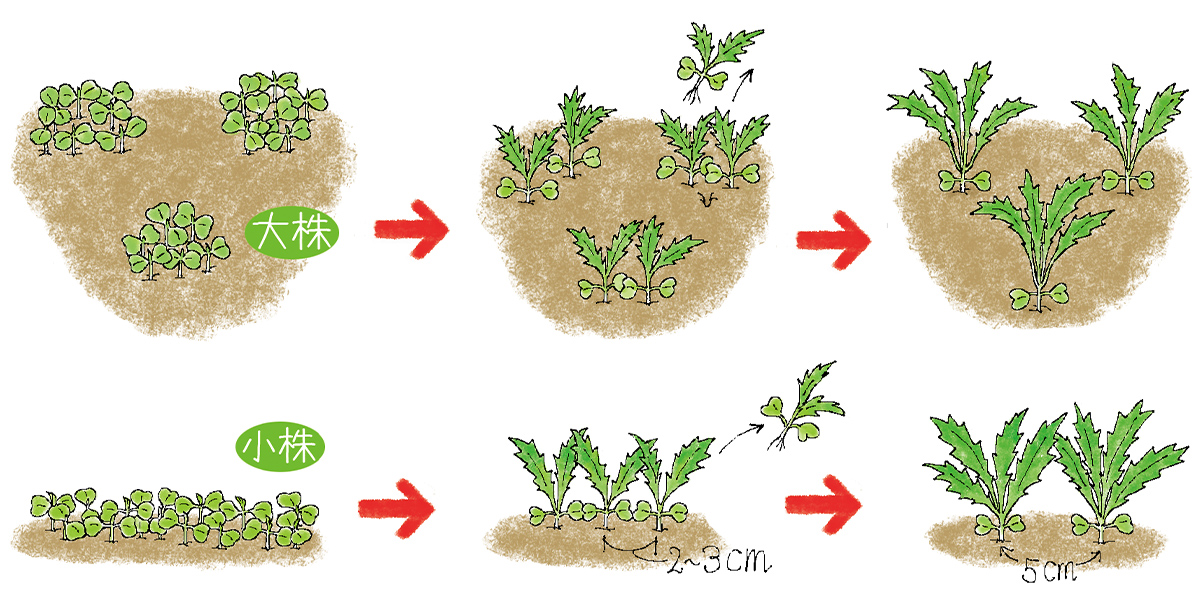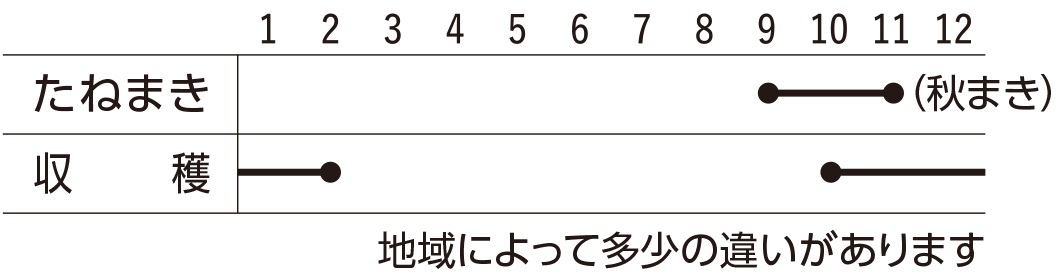材料4人分(12個分)
- しいたけ(直径約5cm) 12枚
- 鶏ひき肉 200g
- おろししょうが 小さじ2
- 酒 大さじ2
- 塩 小さじ1/2
- 片栗粉 大さじ2
- 溶き卵 1個分
- 小麦粉 適量
-
甘酢
- 酢、しょう油、砂糖、水 各大さじ2
-
タルタルソース
- ゆで卵(みじん切り) 2個
- たまねぎ(みじん切り) 100g
-
しょうがの甘酢漬け
(みじん切り) 1/2〜2/3カップ - マヨネーズ 大さじ4
- 揚げ油 適量
作り方
しいたけは石づきを切り落とし、軸はみじん切りにする。
ボウルにひき肉、1の軸の部分、しょうが、酒、塩、片栗粉を入れてよく混ぜ合わせ、12等分にする。
しいたけの傘の裏側に片栗粉(分量外)を薄くふり、2をのせ、水で濡らした手で押さえてひき肉を貼りつける。残りも同様にする。
ボウルに甘酢の材料を混ぜ合わせる。別のボウルにタルタルソースの材料を混ぜ合わせる。
揚げ油を170~180度に熱し、3のしいたけの全体に小麦粉をまぶして溶き卵に通し、ひき肉の面を下にして油に入れ、3分程揚げて裏に返して2~3分揚げて取り出し、残りも同様に揚げる。
5が熱いうちに4の甘酢にからめて器に盛り、タルタルソースをかける。