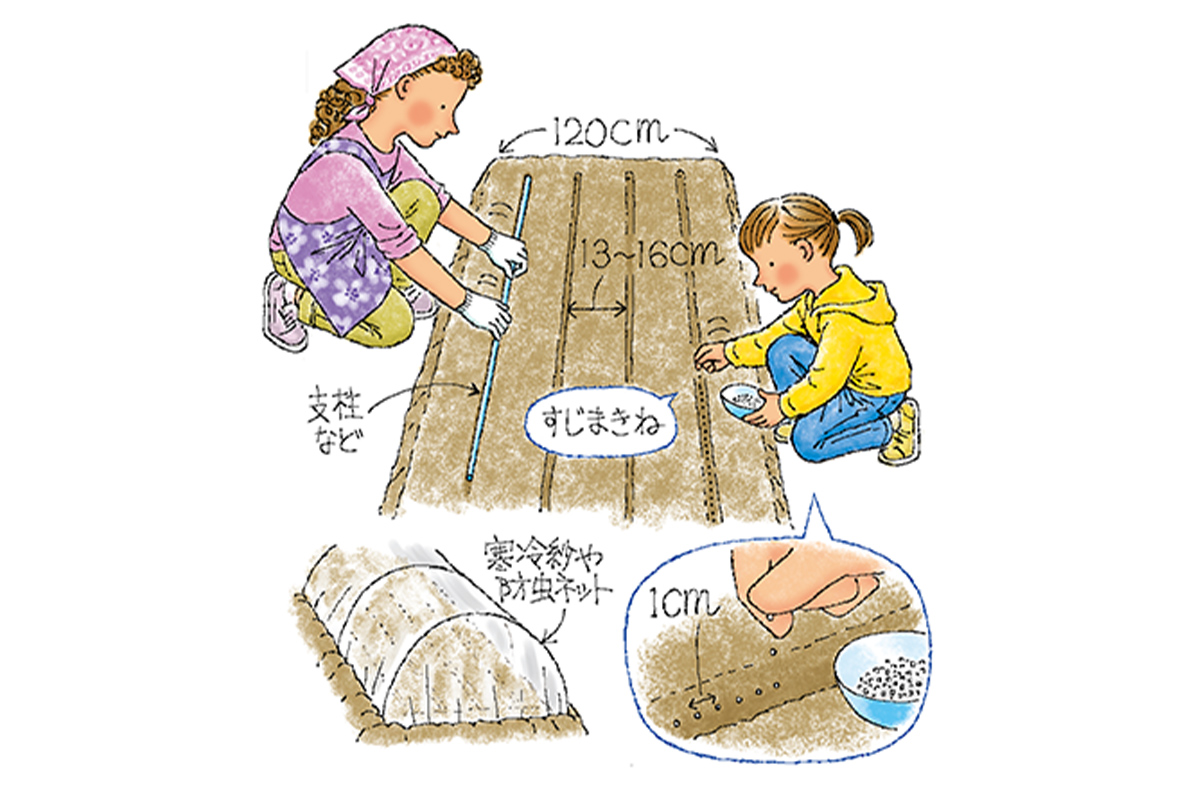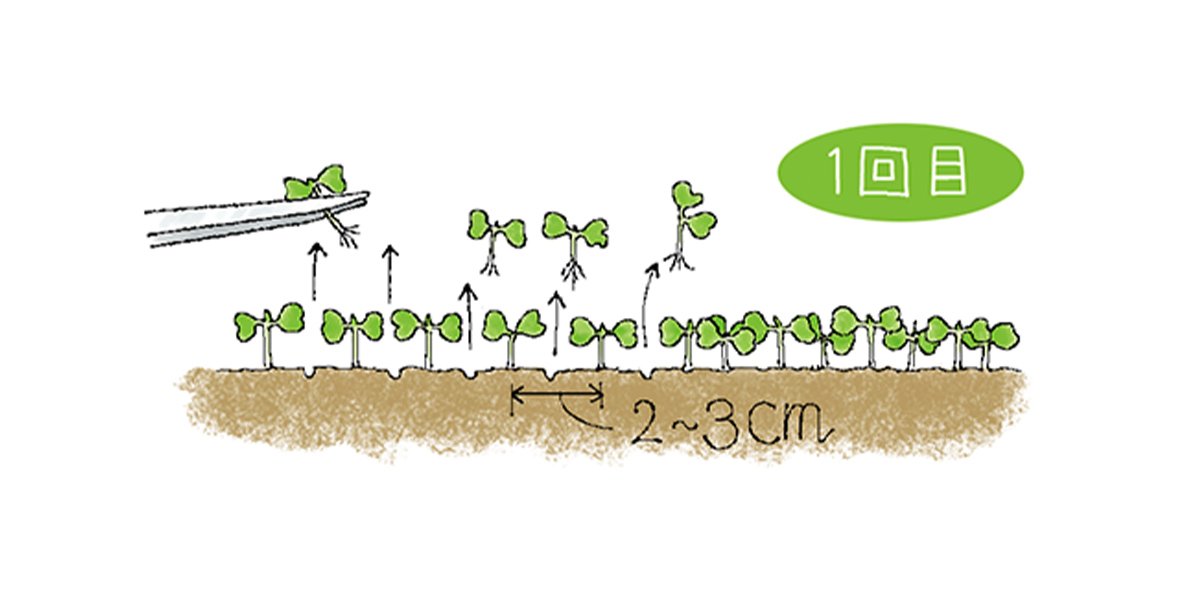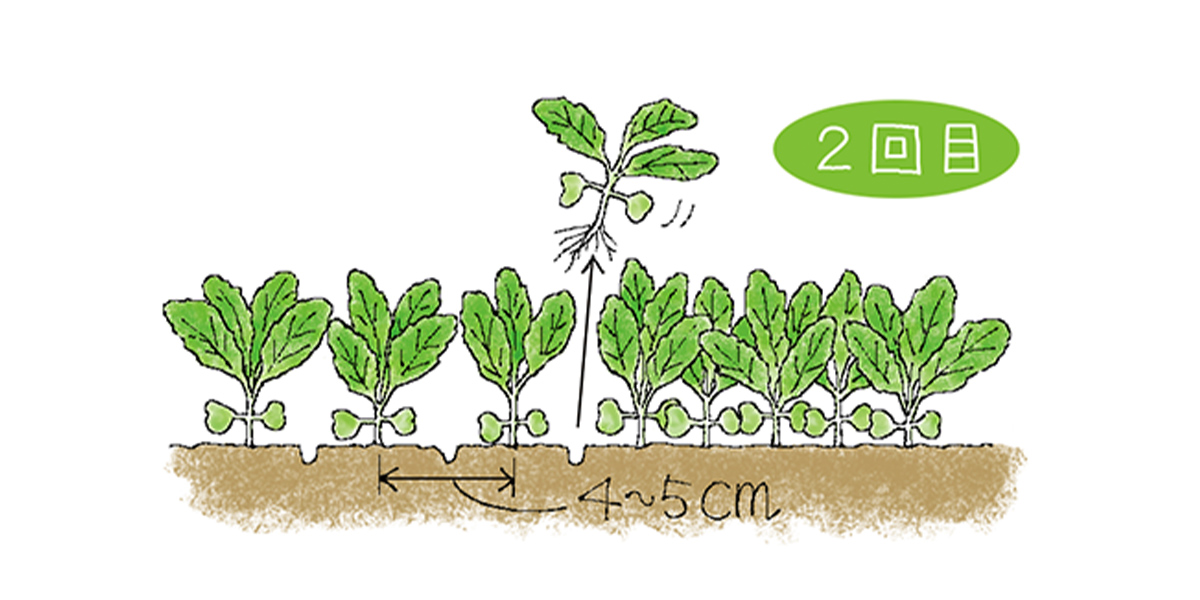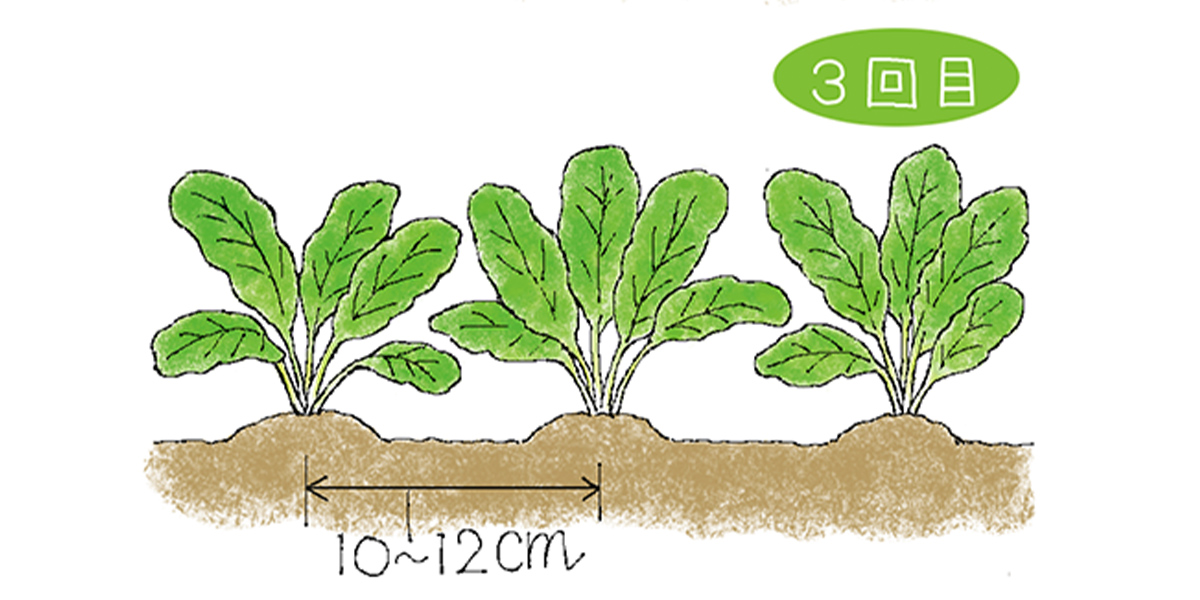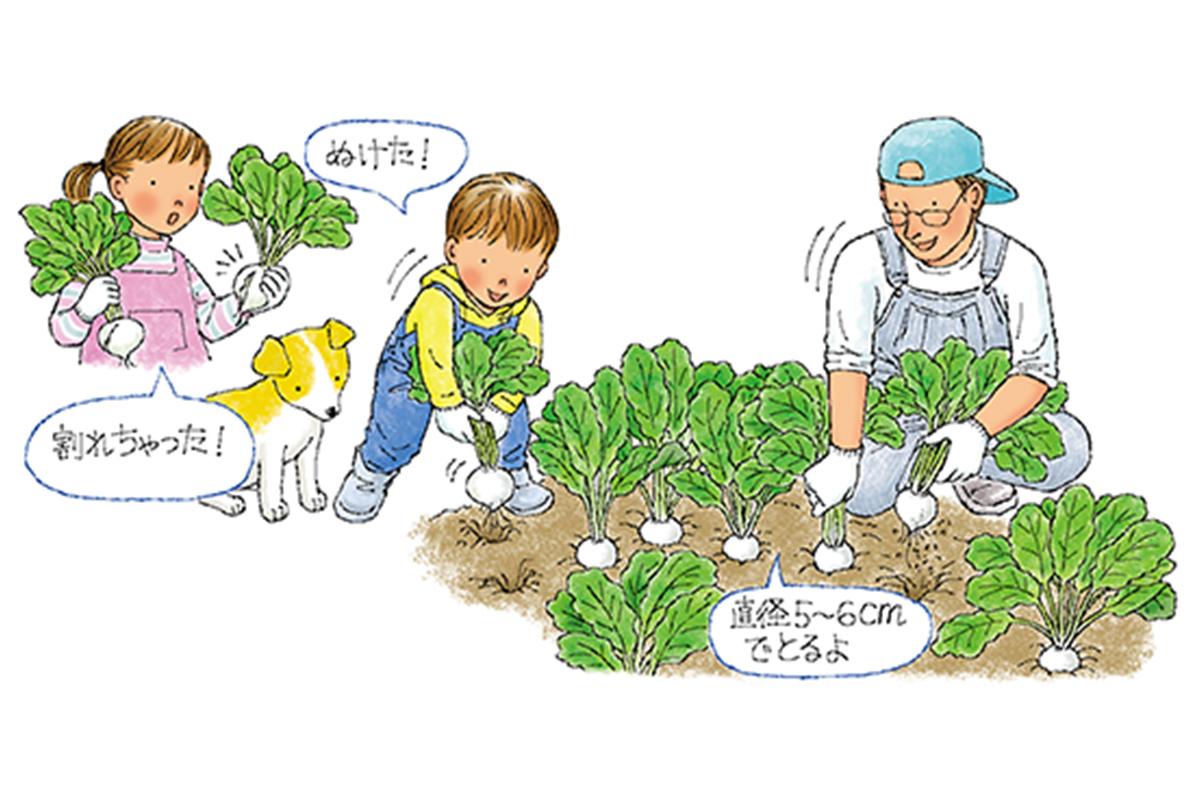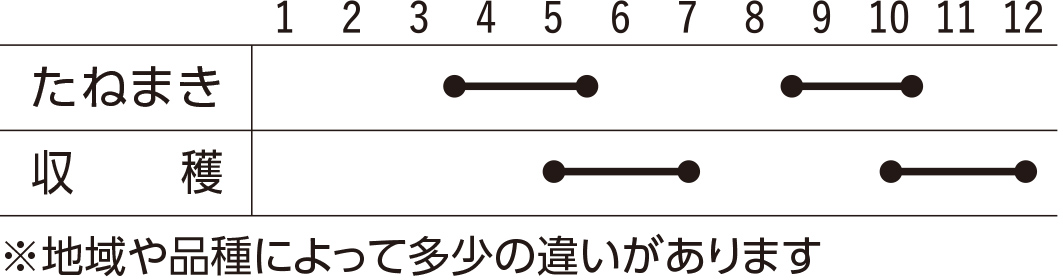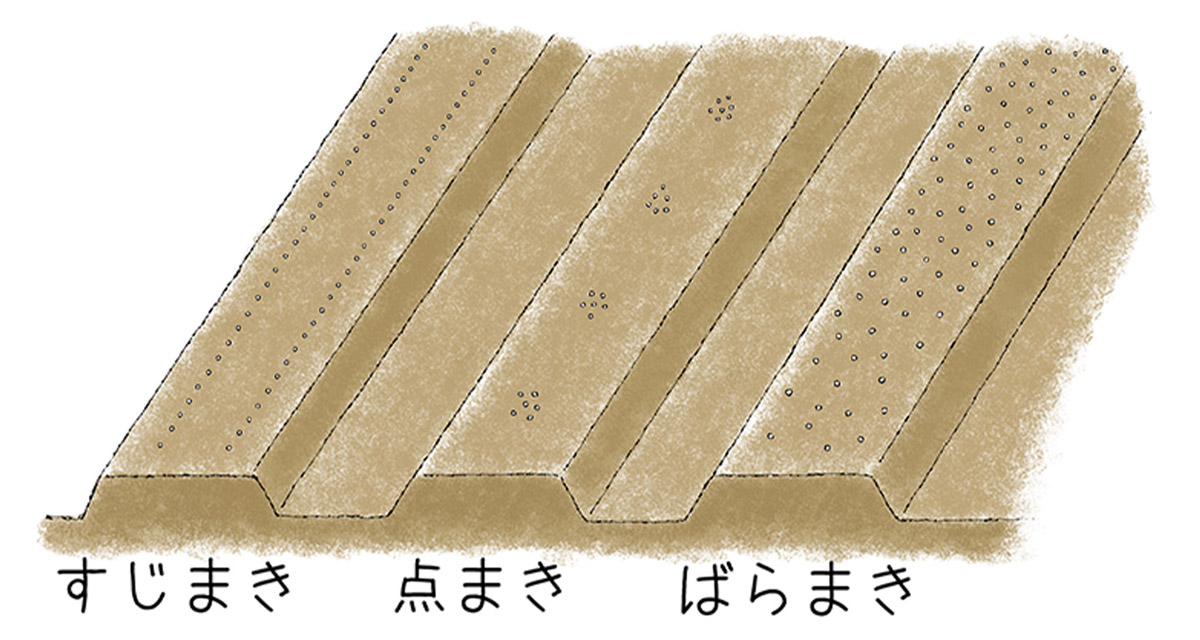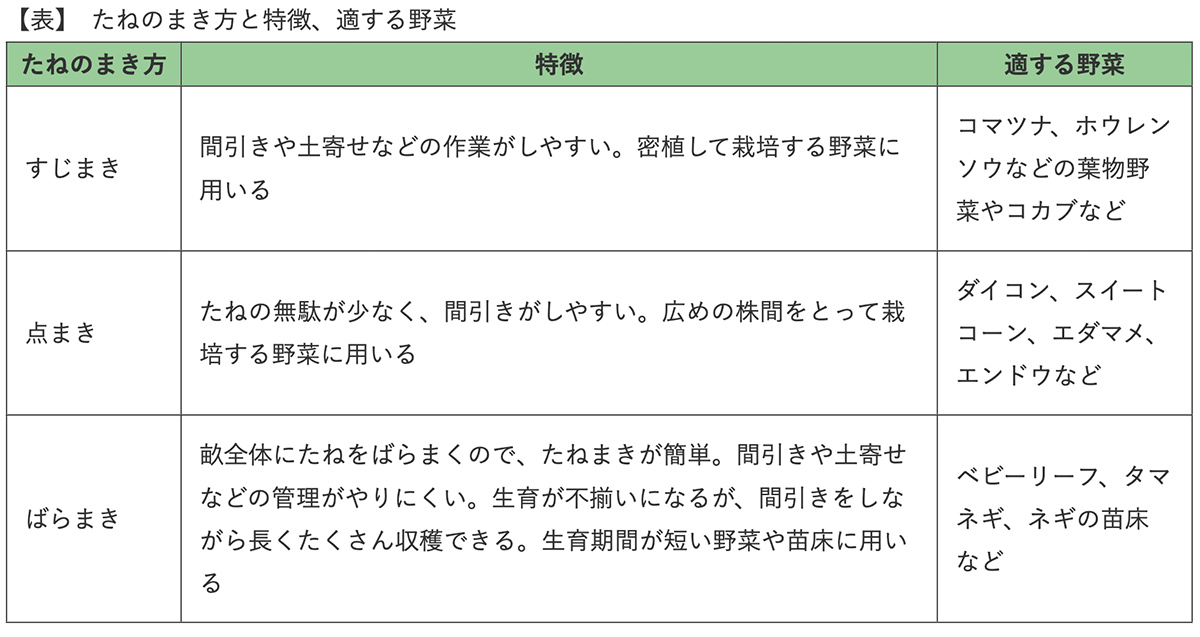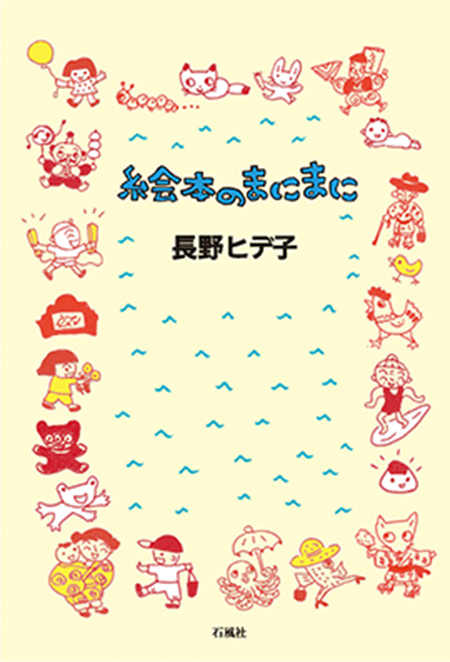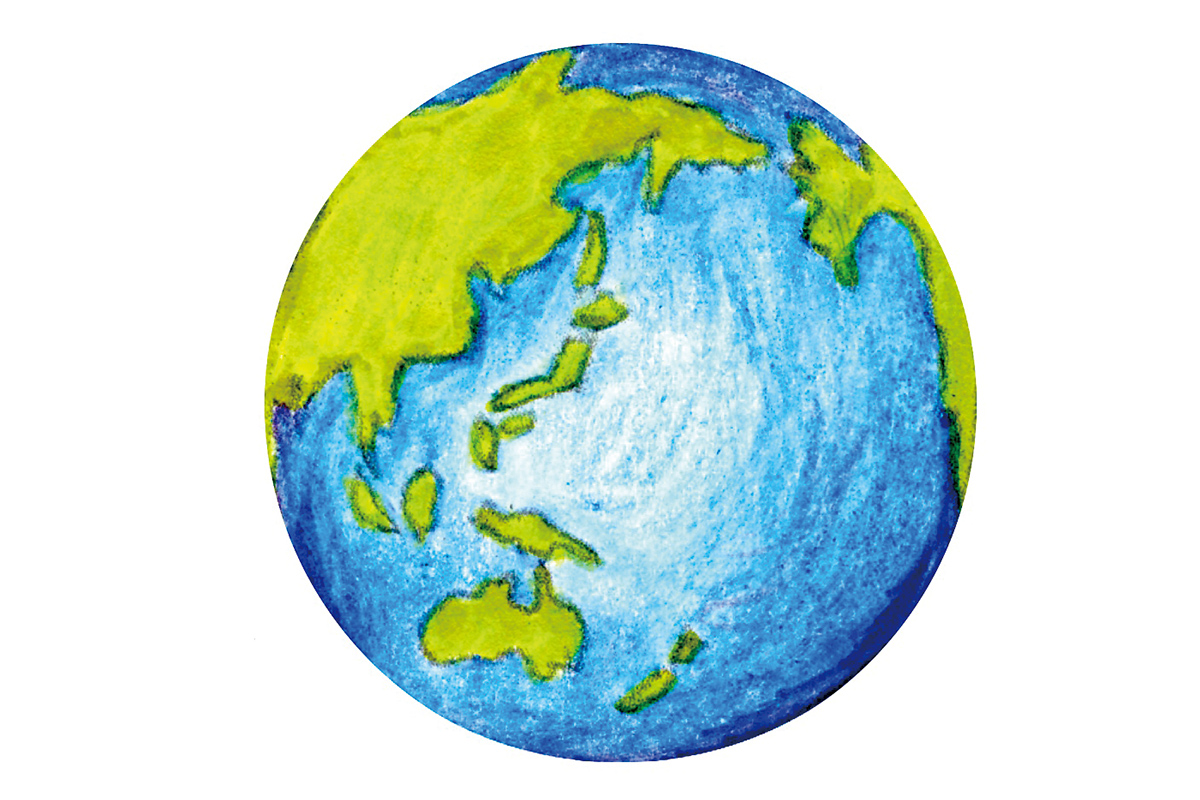大阪府の北部に位置し、兵庫県丹波篠山市に隣接する能勢(のせ)町では、地名を冠して「能勢栗」と呼ばれるほど、栗が有名です。
能勢町は“栗の王様”といわれる品種「銀寄栗」発祥の地という歴史があります。
歴史ある銀寄栗をたくさんの人に食べてもらい、後世に継承していきたいとブランド化に取り組むJA大阪北部を訪ねました。
250年以上の歴史に育まれる

栗は木になる実なので農林水産省では「果物」に分類しています。イガが皮、固い鬼皮が果肉、私たちが食べる実の部分は種にあたります。
能勢町は大阪府の北端、里山に囲まれた山間地です。古くから、日当たりの良い山の斜面を活かして栗栽培が行われてきました。銀寄栗は大粒で甘く、マロングラッセなどの高級菓子にも使われる人気品種です。
「江戸時代中期、現在の能勢町倉垣の村人が良い実をつけた栗の木を増殖させていました。当時は名もない栗でしたが、飢饉の時に高値で売れて、銀貨の上の銀札を集めたことから、銀寄栗と呼ばれるようになったといわれています。飢饉を救ったこの原木は1998年頃に朽ちたのですが、接ぎ木した2世、3世の木が今も倉垣地区で育てられています」と、JA大阪北部営農生活部営農課の西村みつきさん。
他の品種の実と比べて、銀寄栗の実はお尻の部分(座)が大きく湾曲しており、大きな実は一粒25~35gあります。
「1月の剪定や土づくり、4月の接ぎ木、5~8月の草刈り、7月後半の実肥えのための施肥、8~9月の下草刈り、10~11月のイガ焼却など季節ごとに作業があります。また、年間を通して鹿や猪などの獣害対策も欠かせません。大粒の栗づくりにはこまめな手入れが必要です」と、能勢栗振興会の西田彦次副会長。5~6月にヒゲのような雄花と小さなイガの形の雌花が咲きますが、同じ品種では受粉しにくいので、園内に複数の品種を植えます。
「栗は直射日光の当たる枝に実をつけるので、剪定は重要です。定期的に講習会などを実施し、生産者一丸となって技術向上を目指しています」と、JA大阪北部の西村さん。冬の枝ぶりから、新芽が伸びる方向、実の位置まで想定して剪定することが、秋の収量増加につながります。
一粒ずつ丁寧に栗拾い


斜面沿いの栗園では、枝の先に丸いイガが集い、所々艶のある実が顔を覗かせています。
「能勢高等学校(現在:豊中高等学校能勢分校)の農業科で栗の接ぎ木を習い、祖母の栗園で試したらうまくいって、家の苗木づくりを任されるようになりました」と栗栽培のきっかけを話してくれた西田副会長。以来、60余年にわたって栽培を続け、現在は銀寄栗を約30アール、ぽろたんや伊吹など他品種も含めると約50アールの栗園を営んでいます。
「銀寄栗は9月下旬~10月上旬までが収穫期です。空梅雨で猛暑だと早まるので、生育状況を観察しながら収穫します」と、西田副会長。栗は虫がつきやすく、イガについた虫に実を食われると出荷できないので、防除は欠かせません。また、完熟するとイガが自然に落ちるので、猪などに食べられないよう電柵を張り巡らせます。収穫は毎日、朝と夕方に園内を見回り、先端にカバーのついた火ばさみを使って傷をつけないよう一粒ずつ拾い集め、品種ごとにまとめて10時までに選果場に出荷します。


【下】選果場では、虫食い、実入り具合、鮮度などを一粒ずつ人の目でチェックし、選果機で大きさを分別します
選果場では、まず燻蒸してからS、M、L、2Lサイズに選果機で分別。地域全体で大粒化を進めており、幅が3.9mm以上ある3Lも増えています。
「甘くて食べ応えのある銀寄栗の産地として、能勢をもっと多くの消費者の皆様に周知していきたいです」と、JA大阪北部の西村さんはブランドの確立に意欲を見せます。
最後に、2021年から『西田流栗塾』を始め、後継者育成に力を注ぐ西田副会長におすすめの食べ方を伺いました。
「定番の焼き栗のほか、煮崩れしにくいので、肉じゃがのじゃがいもを栗に変えた肉栗もおいしいですよ」。
ペースト状にして生クリームを加え、モンブランを手作りするなど、贅沢な旬の味わいを楽しみたいですね。すぐに食べない場合は、鬼皮のまま新聞紙に包んでから冷蔵保存すれば水分が保たれます。豊かな香気と余韻の残る甘味をぜひお楽しみください。
(取材:2022年9月下旬)

●JA大阪北部
【銀寄栗】生産概要
生産者:140名
栽培面積:130ヘクタール
出荷量:約3.8トン(2022年実績)
主な出荷先:大阪府内