二十代の頃、東北地方に転勤した経験のある友人から「いちご煮」の話を聞いた。「いちご喰うか?」とたずねられ、彼の目の前に出てきたものは、苺とは似ても似つかぬ吸い物。青森県の八戸市周辺や三陸海岸のほうでは、「いちご煮」と呼ばれる、雲丹と鮑が入った郷土料理があるのだ。名前の由来は「雲丹が朝靄にかすむ野苺のように見えたから」だと、あちこちに出ているが、その友人は「むこうじゃ、特別なごちそうを『いちご』と呼ぶんだよ」と、得意げに語っていた。いちご、イチゴ……苺は特別なごちそう、という言葉が、頭に刷りこまれたのは、そのときだ。
それから数年後、私はアムステルダムに引っ越した。1980年代半ばの、マイナス15度まで下がる冬の寒さに、東京育ちの私は震えあがった。やがて春を知らせる合図のように、街角に苺が出まわり始める。ストリートマーケットの屋台の黒板には「Verseaardbeien(新鮮な苺)」と、チョークの字が躍り、お菓子屋のウィンドウには、真っ赤な苺をどっさり載せた大きなタルトが並ぶ。厳しい冬を耐えたあとに街角を彩る苺は、宝物のように煌めき、その魔力にあらがえる人などいない。倹約家のオランダ人もお財布のひもを緩めて、いそいそと生クリーム添えの苺のタルトを注文する。誰にとっても、苺は春を祝う特別なごちそうだった。
日本の苺の歴史も、実は「オランダイチゴ」から始まる。飯沼慾斎著『新訂草木図説』によれば、江戸末期(1830年代)に日本に伝来した。長崎の出島で暮らすオランダ人たちが、故郷の味を懐かしみ、取り寄せたのかもしれない。明治5年にフランスから栽培用の品種が入ってきて、日本でも苺の販売が始まったが、当時は高級品だったらしい。昭和に入って、ようやく庶民の手が届くものとなり、戦後はオリジナルの品種や新品種がつぎつぎと生まれてくる。「あまおう」「とちおとめ」「雪うさぎ」……現在、日本には約三百種類の品種があり、「世界全体の品種の半分以上が日本のもの」だとする説もある。伝来からほぼ二百年を経た今、日本は苺大国となった。
洋の東西を問わず、苺はなぜ人をこんなにも惹きつけるのだろう。特別なごちそう、という友人の言葉は、あながち間違いではなかったようだ。

野坂悦子(のざか えつこ)
翻訳家・作家。オランダ語・英語から数多くの児童書を訳している。翻訳作品に『第八森の子どもたち』(福音館書店)、『レナレナ』(朔北社)、『おいで、アラスカ!』(フレーベル館)、『ミシュカ』(静山社)など。創作に、絵本『ようこそロイドホテルへ』(玉川大学出版部)、紙芝居『やさしいまものバッパー』(童心社)等がある。
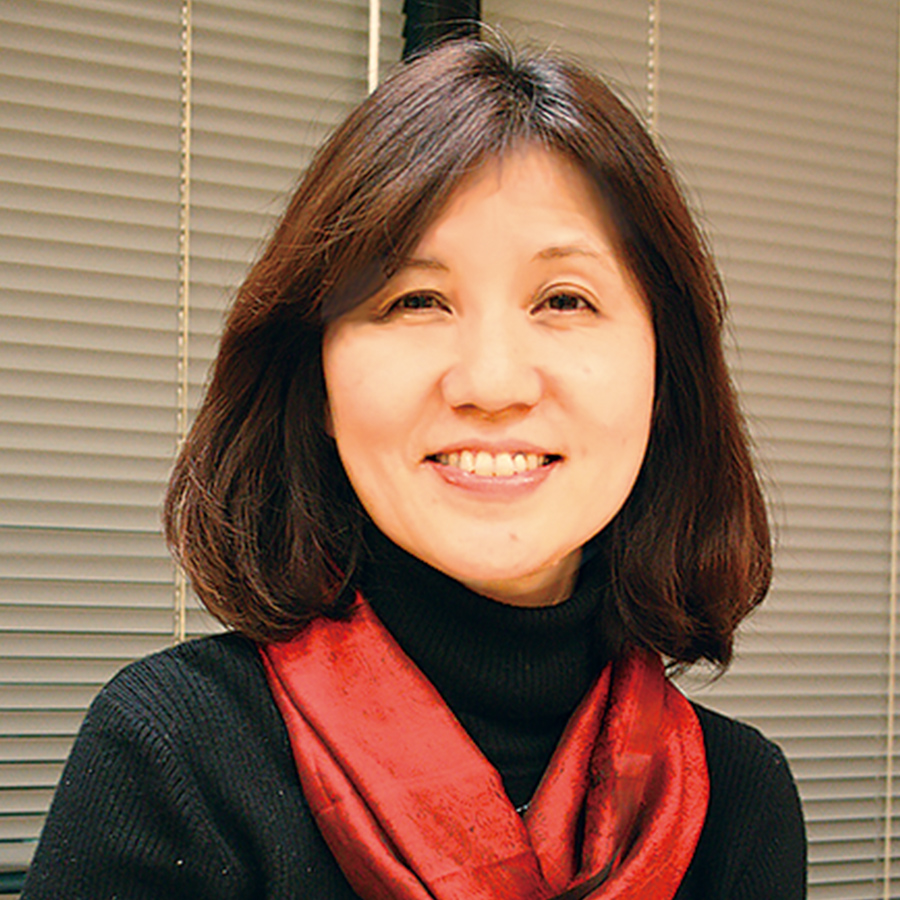

エドワルト・ファン・デ・フェンデル/アヌッシュ・エルマン著
アネット・スカープ絵
野坂悦子訳
静山社
日本ペンクラブ
日本ペンクラブとは、詩人や脚本家、エッセイスト、編集者、小説家など、表現活動に専門的、職業的に携わる人々が参加、運営する団体です。
https://japanpen.or.jp/

