今でこそ冷蔵庫の中身は多国籍になり、無意識のうちに世界中の肉、魚、野菜を食べているが、私の少年時代はもっぱら自分が暮らす周囲の産物を口にしていた。夏の朝、私は母にお使いを頼まれ、近所の農家にキュウリやナスを買いに行ったものだ。腰の曲がった老婆が「今もいでくる」といって、畑に行く。私は薄暗い土間で待っている。五分後、ザルにいっぱいのキュウリとナスを持って、老婆が戻ってくる。それらは母の糠床に入れられ、数時間後、糠漬けになって食卓に並ぶが、その前にキュウリを一本もらい、そのまま齧った。心地よい歯応えとメロンを思わせる香り、ほのかな甘み…それがキュウリ本来の味である。ついさっきまで土に埋まっていた根菜や蔓になっていたトマトやキュウリ、風にそよいでいた葉物のおいしさは畑まで出向かないと、味わえない。優れたシェフのひそみに倣い、たまに畑に出向くと、生産者が蘊蓄を傾けてくれる。近頃のトマトは糖度が高く、美味しいが、栽培のコツは枝についている状態で完熟させること、雨に当てない、余計な水をやらないこと、朝日にも西日にも充分当てることだそうだ。茎部分に無数の産毛が生えているものは空気中の水分を最大限に吸収しようとした証だ。逆境を潜り抜けたトマトこそが甘い。
焼いても、塩揉みにしても、煮浸しにしても、高温の油で揚げた天ぷらでも、味噌と豆板醤で甘辛く炒めても、ナスは人をやみつきにさせる食材だ。それ自体はほとんど栄養がないといわれがちだが、さまざまな味を吸収する完全無欠なスポンジといえる。トマトとナスの原産地はそれぞれアンデスとインドなので、ヨーロッパやアジアでは大航海時代以後でなければ、食べられなかったものだ。ちなみにジャガイモも唐辛子もアンデス由来なので、キムチが赤くなるのも、付け合わせにフレンチフライがつくのも、どんなに早くても十六世紀以後ということになる。
食い意地は博物学に似ている。まだ食べたことのないものをこの舌で味わってみたいという好奇心こそが、生への執着になる。そんなわけでスーパーや市場に行っても、初めて目にする食材の前を素通りできない。
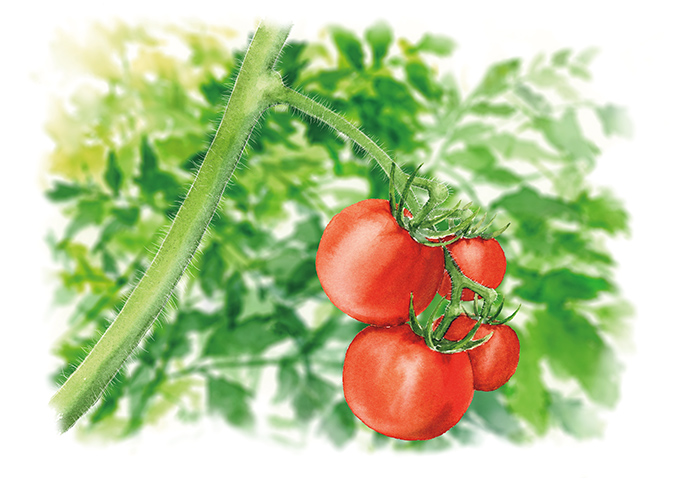

島田雅彦(しまだ まさひこ)
1961年東京都生まれ。主な作品に『夢遊王国のための音楽』(野間文芸新人賞)、『夢使い レンタルチャイルドの新二都物語』、『彼岸先生』(泉鏡花文学賞)、『退廃姉妹』(伊藤整文学賞)、『悪貨』、『虚人の星』(毎日出版文化賞)、『君が異端だった頃』(読売文学賞)、『パンとサーカス』ほか多数。
法政大学国際文化学部教授。

文藝春秋











