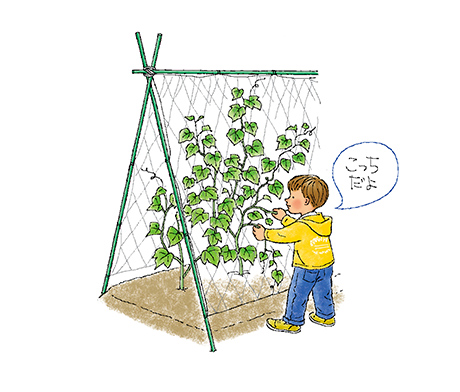「たんくろう」を主力品種に導入

「管内では2005年からえだまめ栽培に取り組んでいます。流通量の少ない黒大豆の『たんくろう』を主力品種に導入し、販売高1億円を目指しています。大豆栽培の経験のある生産者が多いので栽培はスムーズでしたが、収穫後は鮮度が落ちやすく急激な温度変化に弱いため、畑から販売店舗までの徹底した温度管理が欠かせません」と、JAいみず野営農経済部営農指導課の野岸秀旭課長代理。JAでは集荷した枝豆を急速冷却させる保冷庫や選果場を2018年に整備し、集荷から出荷まで低温を保ち鮮度維持ができるようにしています。さらに県行政や全農と連携して、生産者には枝豆専用の収穫機や洗浄機などの省力機械を整備し、作付けの拡大を後押ししています。
支援は着実に作付け面積を増やし、農事組合法人ファームふたくちでは2015年に約30アールからえだまめ栽培を始め、2020年は約4ヘクタール、2021年はさらに1ヘクタール増やしました。6つの集落で構成する農事組合法人で水稲、大豆、大麦、えだまめを約150ヘクタール栽培する、ファームふたくち大門本江班の稲垣潔さんは「大型機械を共同利用することで作業時間や労力が軽減できるので、生産拡大ができました」といいます。
徹底した温度管理で鮮度保持

ファームふたくちでは、夜が明けきらない午前3時から6時までが収穫作業時間です。枝から莢をはずす脱莢(だっきょう)機を装備したトラクターで、グングン収穫します。カゴいっぱいに刈り取られたえだまめは、近くの作業場に運ばれ、水洗いしてからコンテナでJAの選果場に出荷されます。
「気温が低いうちに収穫して温度変化による品質劣化を防ぎます。大型機械で一気に収穫できるようになって本当に助かっています。以前は一株ごと手作業の刈り取りで大変でした」と笑う、稲垣さん。3月下旬から6日間隔で時期をずらして種まきをし、7月上旬から9月にかけて収穫が続きます。JAのえだまめ部会では莢の厚さを8~9ミリで収穫するなどの出荷基準を設け、品質の統一と生産者全体のレベルアップに努めています。

JAの選果場に出荷されたえだまめは、真空冷却されたあと、予冷庫で保管し、光選別機と人の目で厳しく選別。徹底した温度管理のもと出荷されます。
「消費者の皆さんから信頼して選んでいただく産地になるために、栽培技術だけではなく、安全・安心に生産が行われたことを示すGAPへの取組みが不可欠と考え、2018年にえだまめ部会として県内初のJGAP(※)団体認証を取得しました」と、JAいみず野の野岸課長代理。生産者・JA・指導員・関係機関が一体となって取り組んだ結果です。さらに、この認証はあくまでも通過点で、今後も継続してより良い農場運営を目指したいと、意気込みをみせています。
(※)JGAP:Japan Good Agricultural Practiceの略。農水省が推奨する農業生産工程管理のひとつ。食の安全や環境保全等に取組む農場に与えられる認証。

栄養豊富で夏バテ防止や疲労回復にも効果的なえだまめ。ゆでるだけで簡単に楽しめ、素材そのものの味わいを存分に味わえる食材です。希少価値の高いJAいみず野の「富山ブラック」をぜひ一度食べて、濃厚な味わいを堪能してください。”えだまめは鮮度が命”買ってきたらすぐに調理することをおすすめします。食べきれないときは、硬めにゆでて保存袋などに入れて冷凍保存も可能です。えだまめごはんやポタージュなどでも楽しめます。
(撮影:2020年8月中旬)
●JAいみず野
【富山ブラック】生産概要
生産者:22組合法人
栽培面積:約35ヘクタール
出荷量:約71トン(2020年実績)
主な出荷先:県内、関東、中京など