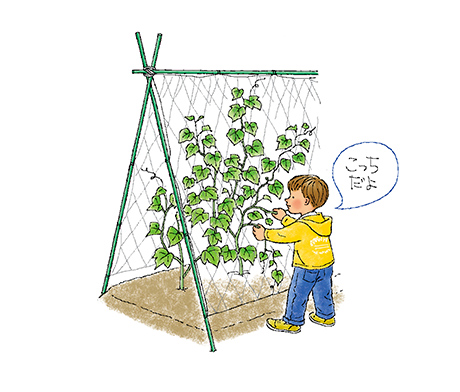夏秋なすと冬春なすで周年出荷

「JAふくおか八女管内のなす栽培は明治末期頃から盛んで、”長崎長”や”庄屋大長”といった大長なすを栽培してきました。1965年以降、施設栽培が導入されて冬春なすの産地化が進むと、中山間地の夏秋なすとともに、長なすの“黒陽”に品種を統一。さらに1991年より”筑陽”へ品種転換し、品質を重視した栽培が行われています」と、JAふくおか八女営農指導部園芸指導課の鵜木晃輝さん。
県南部に位置する八女地域で栽培される「博多なす」は、くせがなくてやわらかく、ボリューム感があって美味しいと人気が高く、地域ブランドを支える中心産地として、作型を組み合わせることで年間を通して安定的に出荷をしています。
「3月から5月に植えつけて、5月から11月まで収穫する夏秋なすと、8月から10月に植えつけて、9月から翌年の7月まで収穫する冬春なすの作型で生産していますので、いつでも美味しい博多なすを味わっていただけます」と鵜木さん。
なすは肥料と水を多く必要とし、温度や日射量などの環境変化に敏感な作物です。高温や低温、日照不足になると受粉不良をおこしやすく、収量が低下します。1つの花の中に雌しべと雄しべがあり、咲けば必ず実をつけるという意味のことわざもありますが、風のないハウス内では交配用のハチを用いた受粉促進や着果促進剤が使われています。着果促進剤の噴霧作業は重労働で高齢化の進む産地では大きな課題でした。
「授粉作業は花が咲いている短期間に集中して行わなければならないので、その労力はかなりの負担でした。2000年頃から高齢化に伴う生産者数と栽培面積の減少が顕著になってきたため、受粉しなくても果実がなる特性をもつ”PC筑陽”(※)という品種の試験栽培を行い、2015年に導入を開始しました」。
PC筑陽の普及拡大で作業の省力化が進むとともに、新規就農者が増えたとも。
「昨年は7名部会員が増えました。新規就農者や後継者を対象にセミナーを開催し、早期の技術習得をサポートしています」と、JAでは産地の維持拡大に向けた取り組みも行われています。
4本仕立てから2本仕立てへ

なす生産者の末廣泰浩さんのハウスは標高300m付近にあります。標高が高いため、朝晩の寒暖差が大きく、つやがよく品質のよいなすができるそうです。
「県内では4本仕立ての栽培が主流ですが、うちは3年ほど前から2本仕立てに変えました。4本仕立てよりも芽吹きがよく、葉が混みあわずに管理がしやすいし、なすの生育もいいです。4本仕立てだと樹勢を維持するために1番果は摘果しますが、2本仕立ては1番果から収穫ができて、トータルで見ると4本仕立てとほぼ変わらない量の出荷ができます」と、末廣さん。

収穫はハウス内が高温にならない早朝4~5時から行い、選果場に出荷します。JAでは2011年に3ヵ所あった選果場を一元化して「なす広域選果場」を建設。カラーカメラによる色彩選別機を導入し、効率のよい選別・出荷作業が行われています。


●JAふくおか八女
【博多なす】生産概要
生産者:約140名
栽培面積:約21ヘクタール
出荷量:約3000トン(2020年度実績)
主な出荷先:近畿、中国、関東など